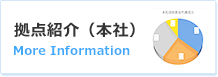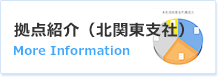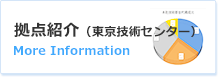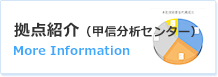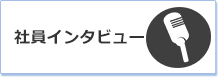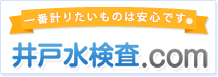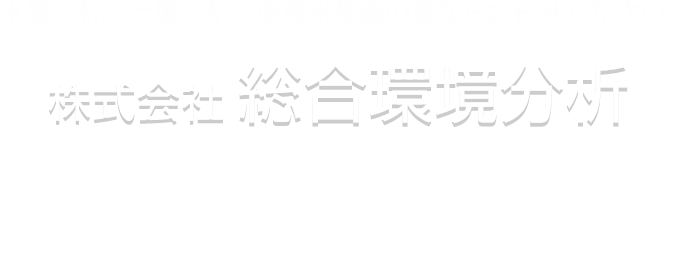計量管理者(環境計量士) 田村規靖*
計量管理者は、分析データの最終確認を行い、データの妥当性を判断し、報告書の品質を保証する重要な役割を担っています。
正確で信頼できるデータを提供することで、お客様の安心・安全に貢献しています。
ー 社員紹介 ー
本社分析センターの主任計量管理者として、飲料水・排水・環境水・産業廃棄物等、主に水質分析を中心に分析データ管理を行い、報告書の発行関連業務に携わっています。

*プライバシー保護のため、名前は仮名にしております。
自己紹介
Q. 環境計量士になろうと思ったきっかけは何ですか?
当初から目指していたわけではありませんが、入社前に業務上必要な資格だと知り、資格取得を目標にしました。
Q. 現在の主な業務内容について教えてください。
計量管理業務に従事しています。
(※当社における計量管理業務とは、飲料水・排水・環境水・産業廃棄物などの水質分析を中心に、分析データの管理や報告書発行の最終確認・承認を行う業務を指します。)
Q. 計量管理の仕事のどんなところに魅力を感じていますか?
総合的に最終的な分析データ判断を行い、その報告結果によって顧客に喜ばれる、または弊社社員の働きがいと誇りを持ってもらえるような重要な業務内容に魅力を感じています。
日常業務・やりがいについて
Q. 一日の仕事の流れを具体的に教えていただけますか?
納期当日午前中までに当日納期の分析データを精査して報告書作成指示を行い、報告書発行確認を行います。
午後は現在抱えている案件対応・当日入荷の検体受け入れの情報収集や指示の周知、翌営業日以降の報告データの事前精査などを行っています。
Q. これまでで、特に印象に残っている計量管理の事例やエピソードはありますか?
私が当時分析業務をしていた頃、フッ素化合物分析において、共存物質の影響によって濃度が低い結果が出たものの、実際は高濃度試料だったことが分かり誤った報告をしかけて、とても動揺したことを覚えています。
また、初めて計量管理業務として河川調査のまとめ報告に従事したことがとても印象に残っています。
Q. 計量管理の業務において、最も難しいと感じる点は何ですか?
何が真値であるのか多くの根拠、材料を収集してより真値に近い報告を行っていく点、また一生懸命分析データを出してもらった分析担当者の採用データを信じる心と逆にその分析データに対して誤りがないか疑いをもって臨まなければならない心との葛藤がある点になると思います。

Q. その難しさをどのように乗り越えてきましたか?
課題について克服することは現在も容易でなく永遠の課題だと思いますが、少なくとも分析データ精査を行う時点でその分析データの妥当性を確認するための判断材料を多く集めることが重要かと思います。
Q. 仕事を通じて、どのような時に最もやりがいを感じますか?
顧客や弊社社員などから感謝や労いの言葉をかけられた時にやりがいを感じます。
また、誤った分析データを顧客に報告しないように自分が『最後の砦』として最大限の重圧を感じながら責任感を持って業務に取り組めることになるかと思います。
専門性・スキルについて
Q. 計量管理において、特に重要だと感じる専門知識やスキルは何ですか?
分析データ(弊社報告書が製品だと仮定して)に対して自分が顧客の立場だったらどのような分析データを提供してもらいたいかを考えることがまずは大前提かと思います。その気持ちがあれば自ずと必要なスキル等は身につけることができると思います。強いて挙げるのであれば下記のようなものが該当するかと思います。
・計量法・JISなどの関連法規の知識
・分析方法の適正な選定とその注意点
・統計的手法の知識
・品質マネジメントシステム(QMS)の理解
・トレーサビリティの確保・理解
・リスクマネジメントの視点
Q. 最新の分析技術や法規制など、常に情報収集を行っていますか?またどのように行っていますか?
インターネットでの検索が断然多いです。環境省や厚労省等のメールマガジンも利用していますが、うまく活用ができていないのが正直なところです。
Q. チームでの仕事が多いと思いますが、コミュニケーションで工夫している点はありますか?
自分は分析担当者に正しい分析データを提供してもらうために、分析担当者にとって耳の痛い話をしなければならず、嫌われ役であることを認識しています。したがって挨拶や丁寧な対応、感謝の意をなるべく多く伝えるように意識していますが、まだまだ努力不足であります。
Q. これまでに経験した中で、最も困難だった技術的な課題は何でしたか?またどのように解決しましたか?
初めての自治体における海洋関連に関する調査の結果報告やまとめ、データ量が多く、考察が含まれた案件には現在も苦労しています。解決については詳しい方に教示してもらう、またはそれらを参考に自分なりに考え解決していく。または過去資料が存在していればそちらを活用して対応しています。
社会的意義・責任について
Q. 環境分析が社会に与える影響とは何だと思いますか?
様々な影響があると思いますが、下記について業務として身近に感じることがあります。
1. 安全・安心の確保
環境分野、医療や食品産業では、分量や濃度などの正確な測定が人命に関わることもあります。例えば、弊社では飲料水を扱っています。分析データの報告ミスによって重大な健康リスクをもたらす可能性があります。
2. 環境・エネルギー管理への貢献
環境分野における水質分析結果が正確でなければ、環境保全の政策・施策の効果を適切に評価できず、環境の維持・改善も進みません。
環境分析業務は、「見えないインフラ・縁の下の力持ち的存在」として社会のあらゆる場面を支えていると考えます。弊社の経営理念である「世界の安心を計る」という面からも環境や健康、安全に至るまで、私たちの生活の根幹を守る重要なものであると考えています。
Q. 正確なデータを出すうえで心がけていることは?
正確な分析データを出すうえで心がけるべきことは、単に数字を扱うだけでなく、「正しい情報=根拠に基づいた判断」を支えるための分析データ収集から適切な処理判断、丁寧さやそのプロセスが重要だと考えています。
将来の環境計量士へメッセージ
Q. 環境問題が変化する中で、計量管理の役割は今後どのように変わっていくと思いますか?
「計量管理」が果たす役割は、これからかなり広がっていくと思います。今までは「数値の正確な把握・証明」が中心でしたが、今後は「測定データをどう使って活かすか?」が重視されていきそうです。
Q. 環境計量士としてさらに磨きたいスキルはありますか?
AIの活用、エクセルのマクロ活用などの基礎知識習得、またここ最近話題になっている分析全般、今後期待され主流になってくる分析方法や分析機器、注目されてくる新規分析項目に関する動向・基礎知識や応用知識を身につけていきたいと思います。
Q. 今後挑戦したい業務や目標はありますか?
弊社にとって次世代の計量管理者の育成と指導がかなり重要な要素だと認識しているのでそちらに尽力していきたいと思います。
Q. これから環境計量士を目指す方へ、アドバイスをお願いします。
まずは資格取得を目指す!これしか道はありません。資格がないといくら知識や経験があっても報告書に印鑑は押せないので。知識や経験は後から否応なく身についてくるので、まずは資格取得のための勉強がとても重要かと思います。(全問正解といった高得点を取らなくてもOK!各分野60点以上であれば合格なので気楽な気持ちで取り組んでいって欲しいです。)
Q. 計量管理の重要性について、読者の方々に伝えたいメッセージ等があれば是非お願いします。

私たちは日々、主に濃度の測定を中心とした業務に従事しています。正確な計量管理は「信頼の土台」であり、「安全・安心の根幹」です。『見えにくいけれど、なくてはならない社会の基盤である』それが計量管理だと考えています。
日常の中で何気なく行う「計る」という行為も、環境分析という仕事の現場では多くの人々の努力と厳密な管理によって支えられています。そうして得られる正確なデータが環境を守っているという事を少しでも知っていただけたら幸いです。
最後に皆さんの貴重な時間を使って、私の計量管理業務に関する考えや思いについて読んでいただきまして、誠にありがとうございました。